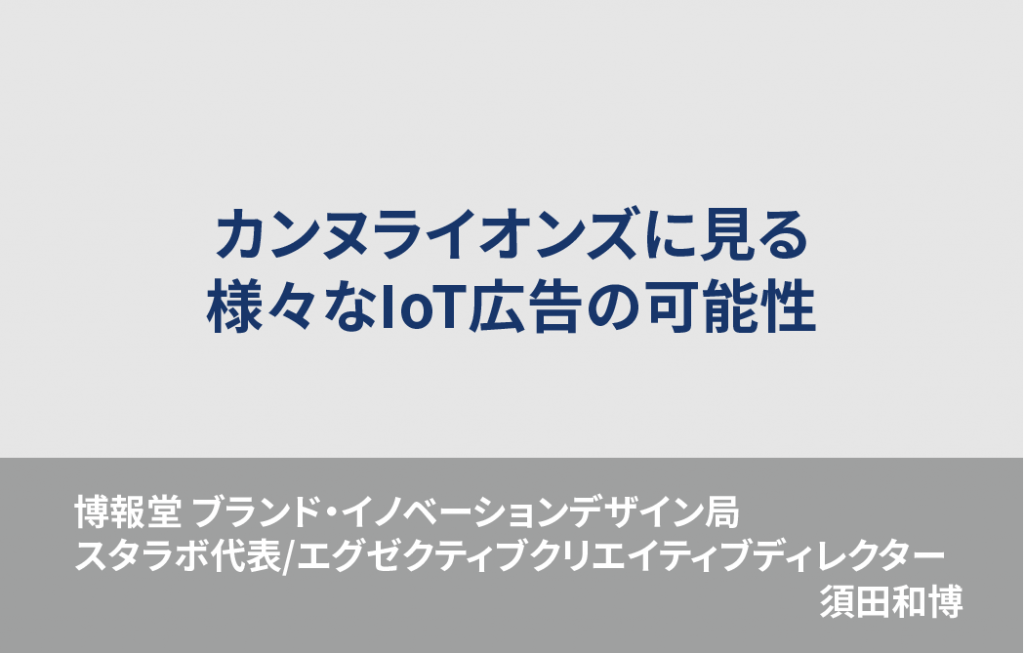
IoT広告のルーツ
IoT時代の広告のルーツをたどっていく時、その原点と言うべきシンボリックな事例は、やはり「NIKE+FuelBand」だろう。カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル(以下カンヌライオンズ)2012年のサイバー部門およびチタニウム&インテグレーテッド部門で、グランプリを獲得した。今や当たり前になっている、「Fitbit」や「Apple Watch」の健康管理アプリなどの御先祖さまのような存在だろうか。
「NIKE+FuelBand」は、その年の1月に発売された「NIKE+」を拡張したオンライン・サービスと製品が一体になったものだ。リストバンドの形をしたプロダクトを腕に着けると、内蔵された加速度センサーが、ユーザーの毎日の活動における運動量を計測し、そのデータをiフォン(iPhone)専用アプリと「Nike+」のサイトに記録する。商品開発の段階からクリエイティブ会社のR/GAが参加し、見事この年のカンヌライオンズを代表する事例となった。
12年当時に計測できたデータは、20年の今の状況に比べてみればとても少なかったが、ユーザーの活動データを企業やユーザー同士のコミュニケーションに活用する手法は、ブランドとユーザーの結びつきを常態化するという事例の先駆けであった。
当時、「これは広告ではなく、製品ではないのか」といった議論があったことを懐かしく思い出す。人々の認識はまだ、広告というものはテレビやポスター、雑誌、インターネットなどの「メディアに掲出されるもの」という理解であった。アップルの「iフォン」発売によってスマートフォンの歴史が始まったのが07年。それが3G対応となって日本に上陸したのは、翌08年の6月である。これにより、個人が行動しながらインターネットと常時接続するのが当たり前になったが、個人にカスタマイズする広告や、行動データに即した情報を提供するサービスが登場するのは、まだ先のことである。
この「NIKE+FuelBand」と、それを「広告コミュニケーション」として高く評価したカンヌライオンズが見せてくれた「広告の新しい地平線」は、その後、確固たるものとして栄え、今では本当に当たり前のものとなった。その間、わずか8年である。今では、様々なセンサーで生体データを計測し、健康というユーザーにとって最も大切なものを維持するために、プラットフォームサービスを受け続けるのも当たり前のことになった。
この傾向は、20年の新型コロナウイルス感染症拡大を経た新しいApple Watchでますます進化した。心拍数、体温、睡眠状態だけでなく、手洗いをしたかどうかも検知するという。また、感染経路を特定するための仕組みを、グーグルとアップルが共同して急ぎ開発したという報道も記憶に新しい。この市場は、今後も確実に栄えるだろう。
余談だが、「ユーザーを健康にする広告」かつ「使ってもらえる広告」の御先祖さまに「ラジオ体操」がある。日本ではNHKラジオで1928(昭和3)年に始まったが、ルーツはメトロポリタンライフ生命保険が、1925年にニューヨークの本社スタジオから放送した体操番組だと言われている。すでに100年近く前から、保険会社が「ユーザーの健康を維持する広告的サービス」を提供していたということは、実に示唆に富む。

事例1 ナイキ「NIKE + FuelBand」2012年サイバー部門・チタニウム&インテグレーテッド部門グランプリ
広告は常に新テックと共に
ラジオ放送は当時「最新のメディア」であった。広告は常にその時代の最新のテクノロジーを、ユーザーに喜んでもらえるように最大限活用する。このことは印刷、放送、インターネット等どの歴史を見てもあきらかである。テクノロジーの進化と、それを「どう〝進化しない人間〟に使うか」に自分は大いに関心がある。
スマートフォンという新しいテクノロジーが出てきた時に、それをどう使うか? VR(仮想現実)やAR(拡張現実)という新しいテクノロジーが普及した時に、それらをどう使うか? それをテクノロジー側からだけでなく、ユーザー側からも考える。つまり、「普通の人だったら、コレどう思うかな?」「普通のお客さんだったら、コレ喜ぶかな?」というところと、技術要件とを行ったり来たりしながら考える。今の言葉でいう「UX(ユーザー・エクスペリエンス=ユーザー体験)」である。
11年にカンヌライオンズでメディア部門のグランプリを受賞したサムスンとテスコ(TESCO)の「Homeplus」は、QRコードの活用で地下鉄ホームをスーパーマーケットに変えた事例だ。日本ではガラケーによって普及した「QRコード」の一般活用だが、世界ではスマートフォンにより初めて可能となった。QRコードは94年に日本のデンソーによって開発され、一般ユーザーが携帯電話でこれを読み取れるようになったのは、日本では02年にJフォン(J-PHONE)で発売された端末からである。
大事なのは、「その技術をどう使うか?」である。勤め先からの帰りに地下鉄ホームで買い物を済ませられたら便利だな。スーパーの商品棚をポスターのように印刷してQRコードを載せたら、直接、商品を買えるんじゃないか? 試しにやってみよう。開発者用語で、これを「ハック」という。手元にありすぐ使えるものを組み合わせて、目的にかなうものをまず作ってみる。そしてユーザーに当ててみる。ユーザーがどう反応するかで、また考えて開発する。スダラボも、ほぼこれである。技術があったらとりあえず使ってみる。「こう使ったら面白いんじゃないか?」という使い方で。そして、ユーザーの反応を観察し「ここがポイントだ!」という勘所を洞察する。それを次の開発に生かす。その繰り返し。

事例2 サムスン・TESCO「Homeplus」2011年メディア部門グランプリ
技術は「どう使うか? 」が大事
この連載で語ろうとしていることも、ほぼそれに尽きる。技術を使って試しに作ってみて、ユーザーの反応から「仮説」を洞察する。プロトタイピングとフィールドワークの往復。いつも思うことだが、「新技術は発明された時は、まだその使い道がわからない」ものだ。自分の好きな喩え話に「ライト兄弟が初飛行に成功した時に人々は『空なんか飛んで、どうするの?』と言った」というものと、「ベルが電話を発明した時に『電話は電信ほど普及しない、ただ声が聞こえるだけだから』と言った」というものがある。
99年に日本で世界初のカメラ付き携帯電話が発売された時に、多くの人はピンとこなかった。「ケータイにカメラなんか付けてどうするの?」と。それが市場に大歓迎されたのは、2000年に出た「メールに写真が添付できる」端末からだった。後にこれは「写メール」と名付けられた。開発当初のコンセプトは「仕事でがんばっているお父さんに、我が子の写真をキレイに簡単に撮って送れるように」だったそうである。この逸話も、とても示唆に富んでいると思う。
データ連携する環境での広告
14年のカンヌライオンズのダイレクト部門のグランプリを受賞したブリティッシュ・エアウェイズの「MAGIC OF FLIYNG」は、今の「データ連携デジタルサイネージ広告」の可能性の端緒を開いたと言える。「#lookup」キャンペーンの一環としてロンドンのピカデリー・サーカスで行われたビルボード広告で、同社の飛行機の高度・緯度・経度などリアルタイムの位置情報と連携し、ビルの上空を飛行機が通過する際、画像の中の子どもが飛行機に手を伸ばす動作をするというもの。かなり大規模で難易度の高い開発だが、アイデア自体は極めてシンプルで、「わぁー、飛行機だぁ」という素直な子ども心を、その瞬間に可視化するものだ。
今では世界の街のすみずみにカメラ付きサイネージが設置され、モニターに映った広告を通りすがりの人が見たか、反応したかなどが計測できる。だが問題は「それが嬉しいかどうか?」である。いつも思うのは「ユーザーは広告を基本的には見たくない。ならば、どうしたら見たくなってもらえるか?」。それを考えるのが広告企画者の仕事である。
環境データとの連携、ユーザーの行動データとの連携、サイネージからの顔認識、ユーザーの位置データからの表示最適化。今やこれらのことはかなりの精度で実現可能である。スマートシティと呼ばれるものならば、ID認証デバイスを持ち歩くユーザーに対して、街中のサイネージがその人に向けた広告を、その人が通る瞬間に表示可能だ。問題は「それが嬉しいかどうか?」である。人間は追跡されて広告を見せられ続けること自体は歓迎しない。ならば、「どうすれば歓迎してもらえるか?」を企画者は本気で考えるべきだ。

事例3 ブリティッシュ・エアウェイズ「MAGIC OF FLIYNG」2014年ダイレクト部門グランプリ
生活者に届くのはアイデア
14年のサイバー部門、メディア部門、デザイン部門を受賞したスウェーデンのドラッグストア「Apotek」のサイネージ広告は、通りすがりの人に喜んでもらえる認証型広告の好例だった。地下鉄の広告サイネージに高周波センサーを取り付け、電車がホームに入ってくる瞬間をとらえ、それまで動かなかった広告画像の女性の髪の毛がブワッと風に舞う。風に乱れてもすぐにスタイルが整うヘアケア商品の広告だ。
地下鉄ホームに風がブワッと吹く瞬間、誰もが思い出せる印象的な日常シーンだろう。その瞬間に最適なアイデア。それが技術連携により実現可能になった。これがつまり「嬉しいかどうか?」だ。生活者に喜んでもらえるかどうかの大事なポイントだ。アウトドア・メディアという「アテンション」が重要な媒体だからこそ、このアイデアは有効だった。従来のグラフィック・ポスターで「〝何〟を〝どこ〟に〝どう〟貼るか?」に加え、「どう反応する紙か?」まで企画できるようになった。技術のおかげで企画の幅が広がった。あとは企画者の出番である。
広告技術環境だけが整備されて、まだ企画者の出番になっていないものが、あまりにも多い。これは今に始まったことではなく、印刷の時代も、テレビの時代も、そうだったに違いない。ただし、顔認証やID認証で広告が高精度にユーザーをターゲティングし追跡できるようになると、企画者が仕事をしていない広告は今まで以上に「嫌なもの」になってしまう。企画者のみならず広告産業にたずさわる者は、全員これを肝に銘じなくてはならない。

事例4 Apotek「Blowing in the Wind」2014年サイバー部門・メディア部門・デザイン部門・受賞
視界そのものがメディアになる未来
18年のデジタルクラフト部門グランプリ受賞作であるビリー・コーガンの「Aeronaut」VRミュージックビデオは、アーティスト本人をボリオメトリックスキャンによって3D撮影し、空間そのものとして体験する次世代エンターテインメントである。これは、3D空間にもアートやデザインの「クラフト性」の高さを求める先駆けを示した。新技術が登場する時、初めは技術そのもので驚いてもらえるが、やがて人間はその新技術による表現に「美」を求めるようになる。
1895年にリュミエール兄弟がシネマトグラフによる世界初の映画上映(商業公開)を行った時の作品である「工場の出口」や「ラ・シオタ駅への列車の到着」は、世界初の実写映画であり、現実世界を映像で再現できるだけで大人気となった。ここから始まった「映像の歴史」は、人々に大いに評価され、やがてモンタージュなどの映像文法を生み、様々な演出術や美を取り入れ「映像芸術」を発展させて今に至っている。
3D-VRはじめ、ARやMR(複合現実)などXRによる表現の歴史は、今まさに始まったばかりである。この技術が人々に歓迎されて普及するかどうかは、それがもたらす「喜び」にかかっている。カメラ付き携帯は「写メール」という喜びと共に普及し、後の「インスタグラム」など、写真でコミュニケーションするSNSへの連綿たる流れとして人間に不可欠のものとなった。XRが今後どうなるかは、実のところ、まだ誰にもわからない。わかっているのは、20世紀初頭にリアルの3次元空間を「2次元の動画」に撮影し再現することで始まった「映像の歴史」が、技術進化によって21世紀初頭に「3次元のまま」撮影可能になったということ。この3次元映像=XRがユーザーに歓迎されるかどうかは、それを「どう使うか?」にかかっている。物語か、体験か、お役立ちか。それを考えるのは今後の企画者の仕事だろう。
おそらく、まもなくスマホARをメガネに表示する技術が快適なUXを獲得し、その時XRが新市場になる時がくる。「メガネXR」が普及すると、視界そのものがメディアになる。そうなった時、広告はその「視界そのもの」に何を表示するのだろう? 企画者の知恵が、さらに問われる時代がくる。
「基本的に見たくないもの」である広告を、「嫌なものは嫌」と言う生活者に、どう見てもらい、お役に立ち、嬉しくなってもらうか? 次世代広告環境が整えば整うほど、そのことに真摯に取り組まない限り、広告は産業として淘汰されかねない。「知らせたい人=クライアント」と「知ってほしい人=生活者」の間に立って、あらゆるメディアやテクノロジーを縦横無尽に活用しながら、双方にとって喜ばれるものを提供し続ける。常にその未来の可能性を指し示すカンヌライオンズを見ればわかるように、従来のメディアの中だけでなく、広く日常のすみずみにまで拡張した21世紀の広告領域は、とても扱うのが難しい反面、とても大きな可能性に満ちている。大変だけど、やりがいのある仕事だな、と思うゆえんである。

事例5 ビリー・コーガン「Aeronaut」2018年デジタルクラフト部門グランプリ
